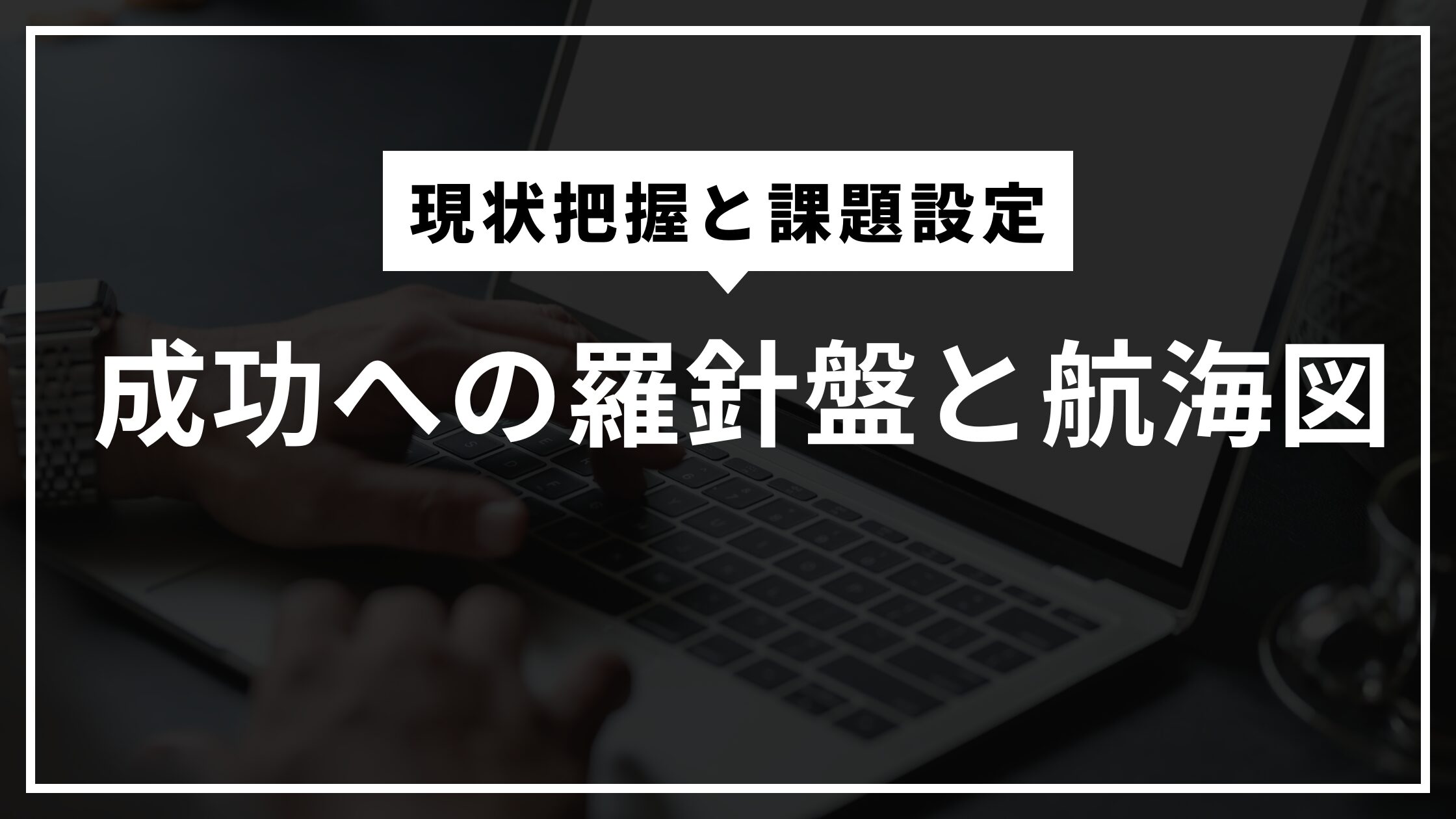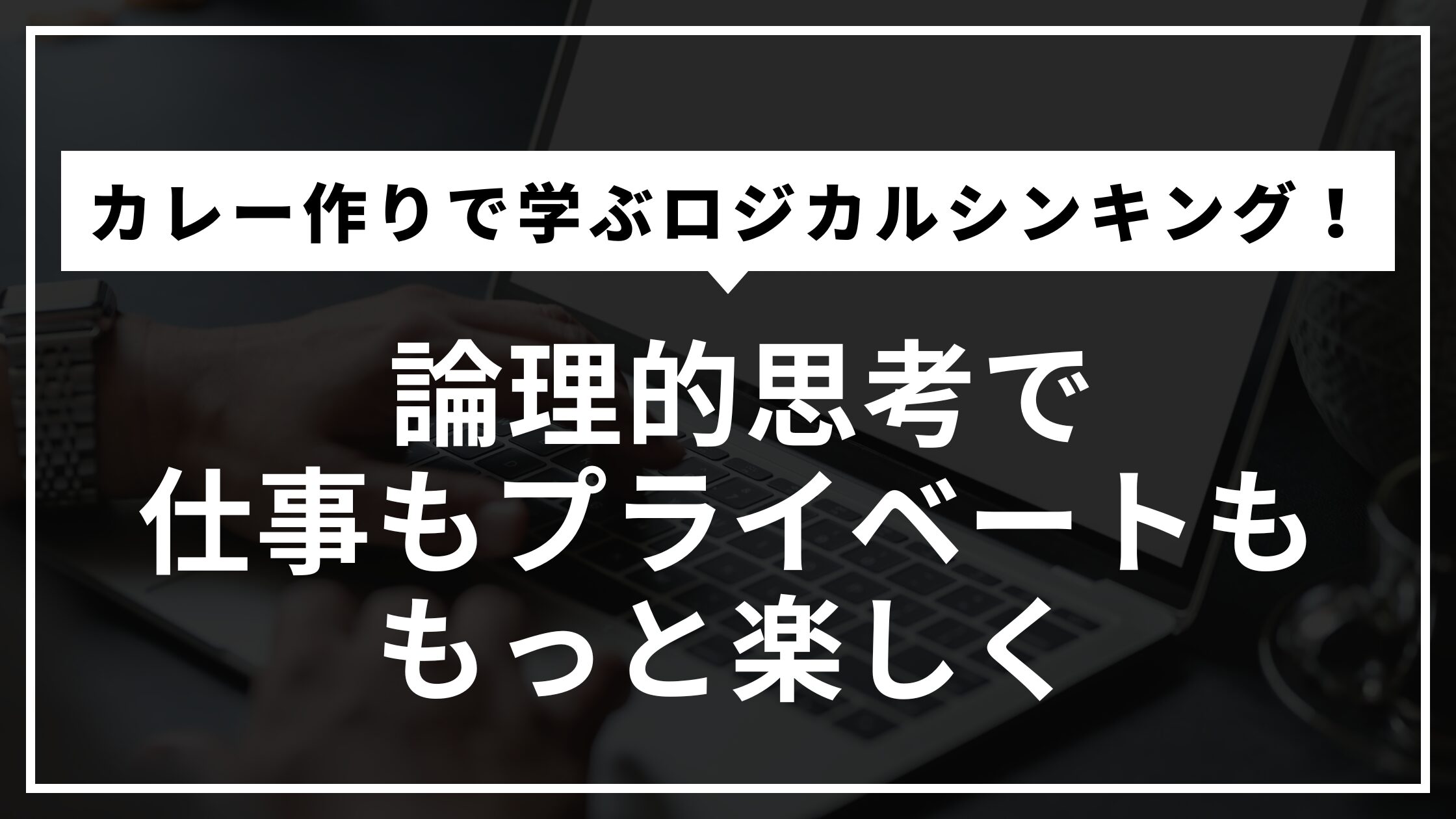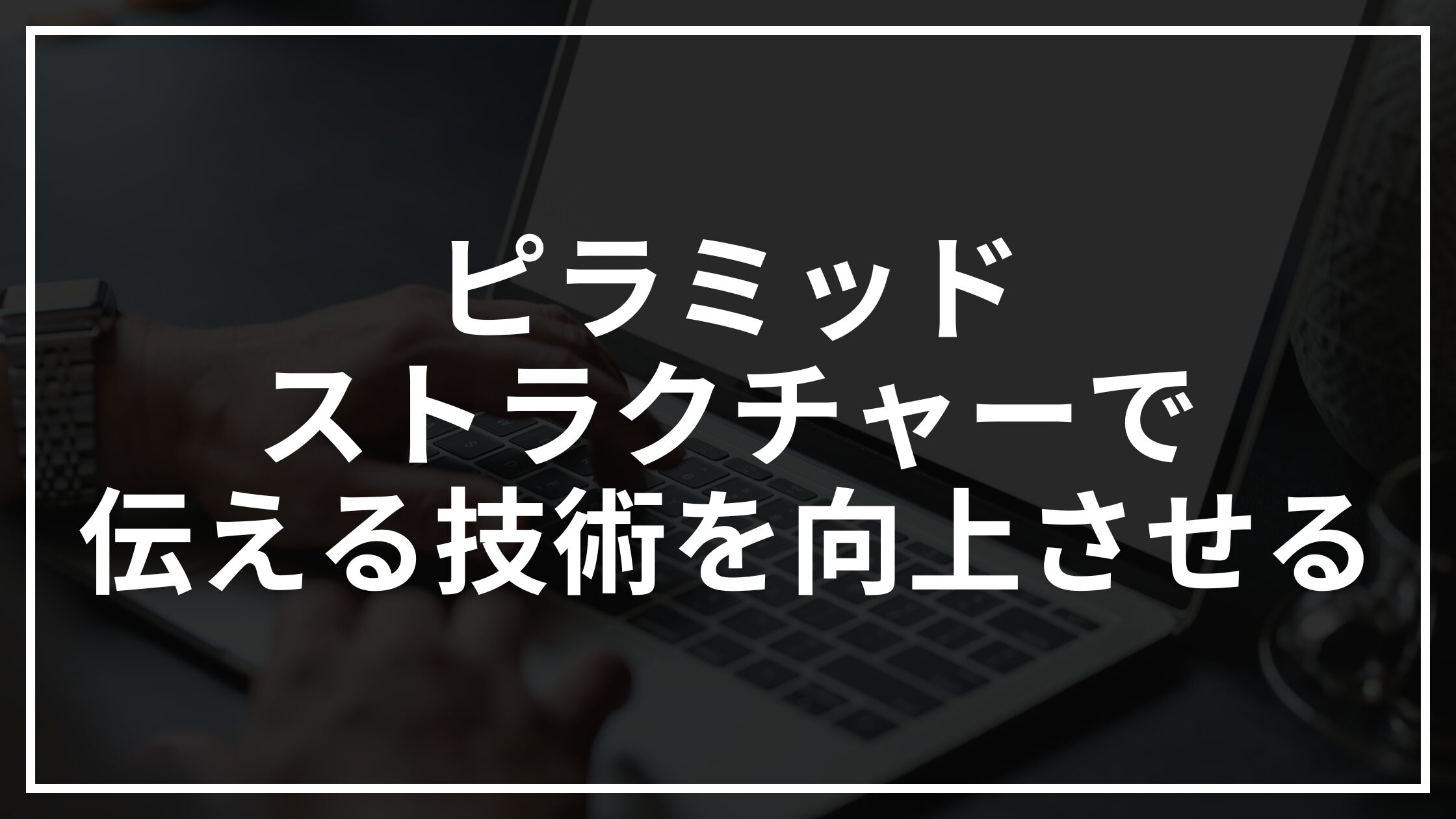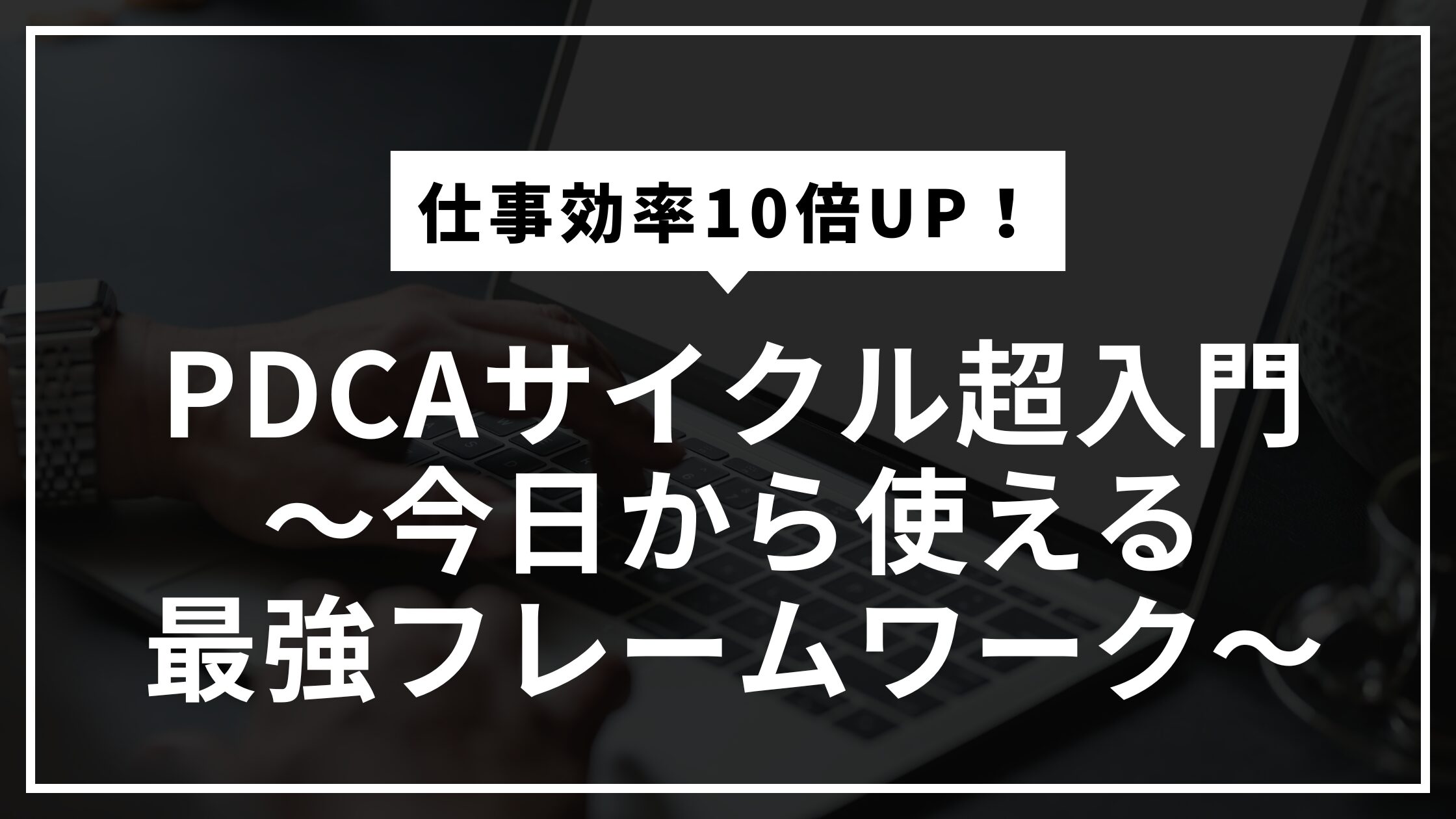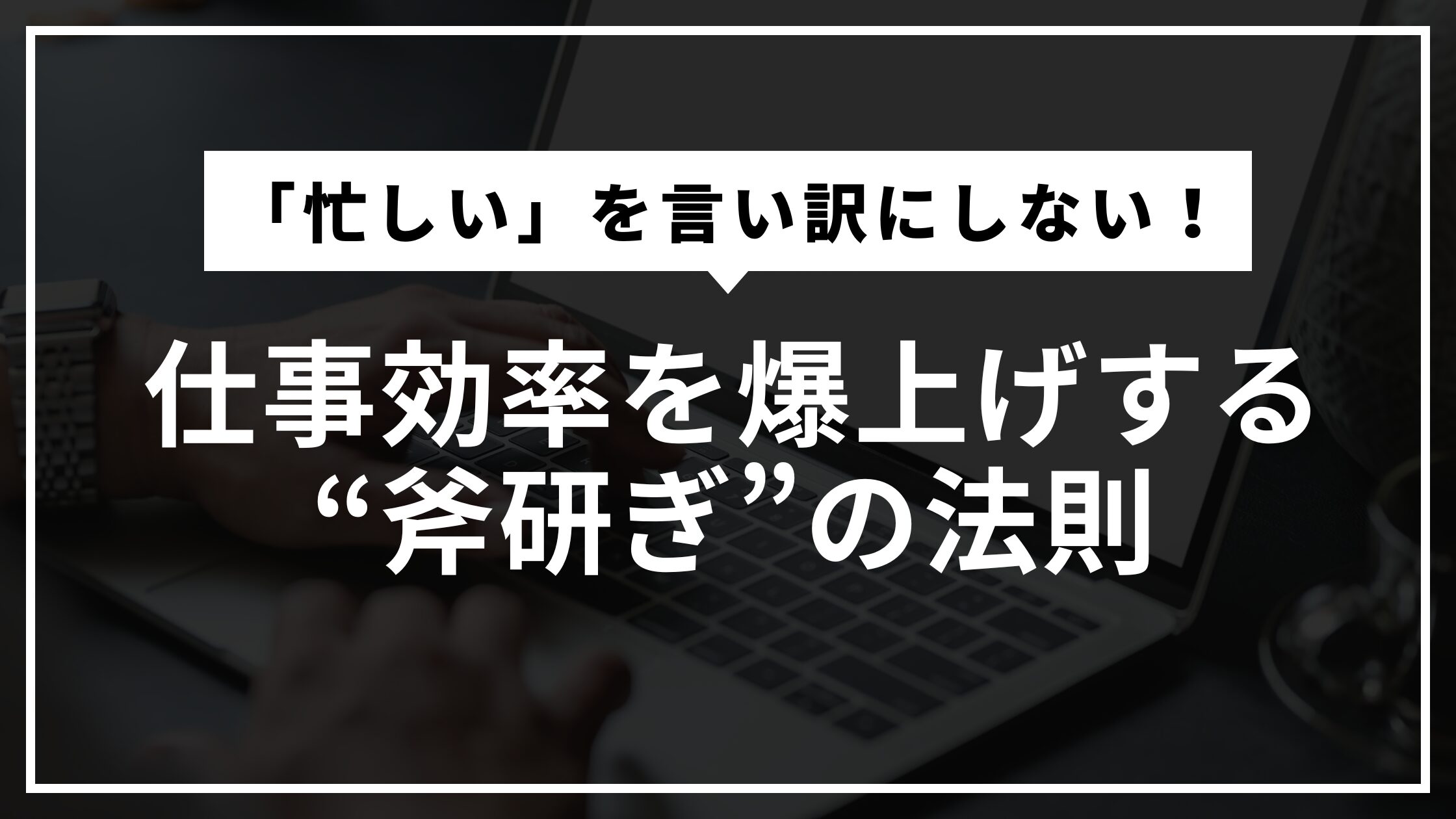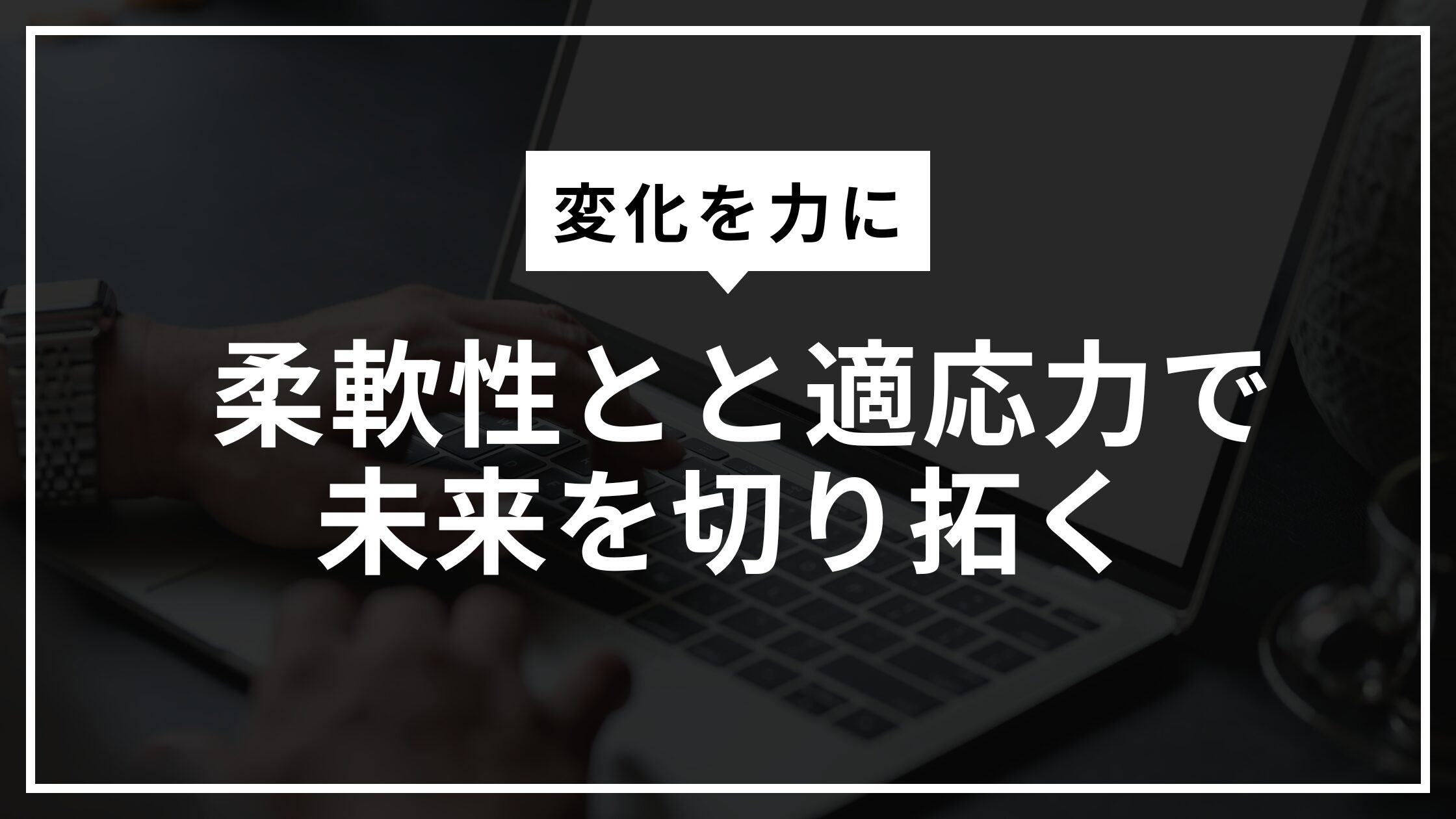MECEの概念をカレー作りでマスター!論理的思考が劇的に変わる!
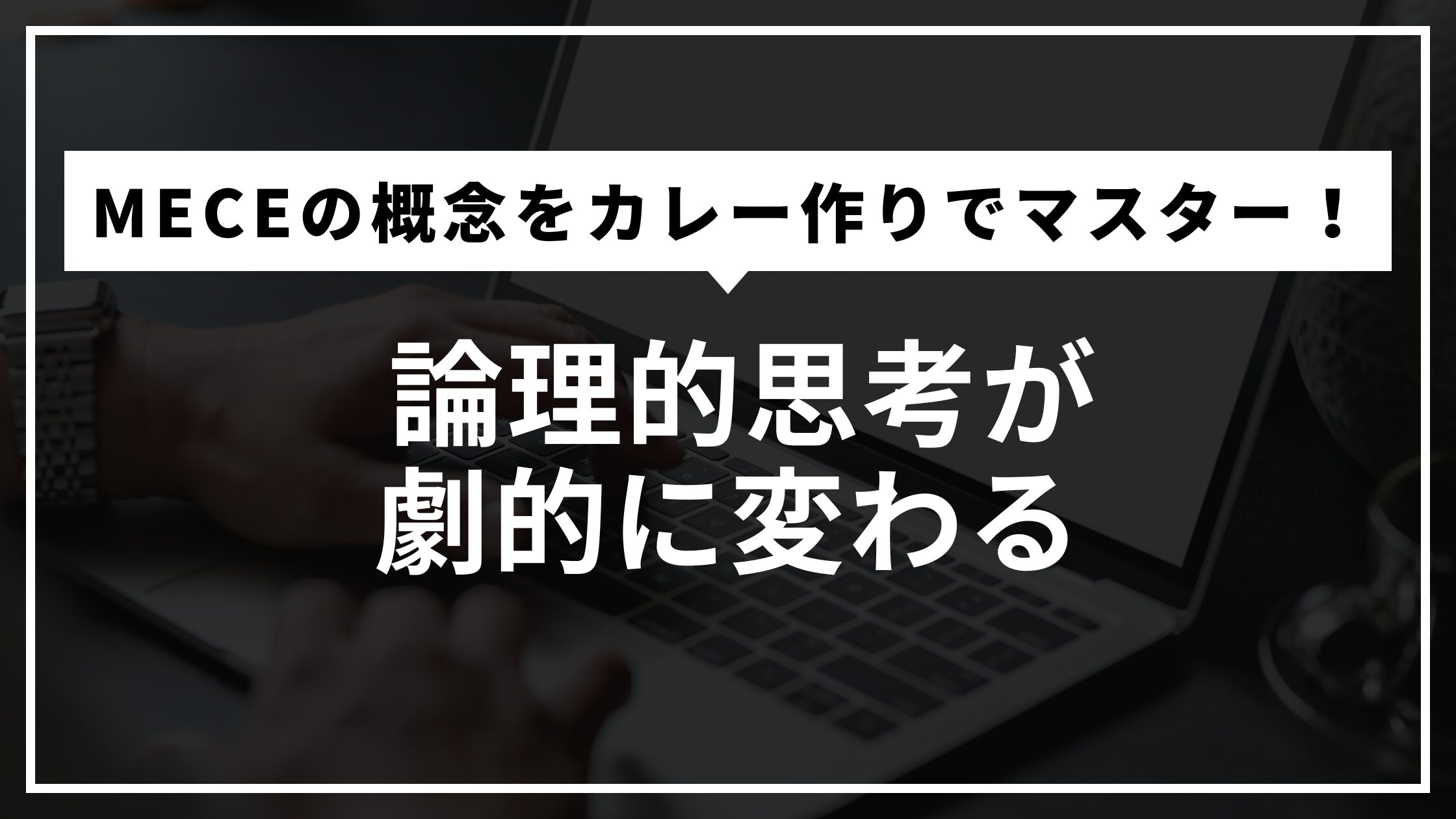
皆さんはMECE(ミッシーまたはミーシー)という言葉をご存知でしょうか?
ビジネスシーンでよく耳にするこの言葉は論理的な思考をする上で非常に重要な概念です。今回は、MECEの概念をカレー作りという身近な例えを用いてわかりやすく解説していきます。
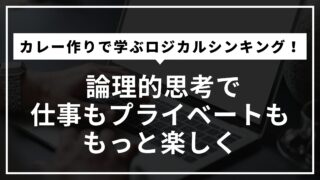
MECEとは?
MECEとは「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字を取った言葉で、漏れなく、ダブりなくという意味です。
つまり、物事を分析したり、課題を洗い出す際に、全ての要素を漏れなく網羅しつつ、重複する部分がないように分類することです。
カレー作りで考えるMECE
MECEの概念をカレー作りに当てはめて考えてみましょう。
MECEに沿った良い例
カレーの味があまり美味しくないという問題に対して、MECEに沿って要素を分解すると以下のようになります。
| 素材 | 野菜、肉、スパイス |
| 調理方法 | 切る、炒める、煮込む |
| 配合 | スパイスの量、水の量 |
| 味付け | 塩、コショウ、その他調味料 |
このように、カレーの味に影響を与える要素を漏れなく、かつ重複なく洗い出すことで、問題の原因をより深く理解し、改善策を立てられます。
MECEに沿っていない悪い例
MECEに沿っていない例としては以下のようなものが挙げられます。
| 素材 | 野菜、肉、スパイス、玉ねぎ、ニンジン |
| 調理方法 | 炒める、煮込む |
| ~その他は省略~ | |
この例では、以下の問題点があります。
- 重複
「素材」の中に「玉ねぎ」「ニンジン」と具体的な食材名が含まれているため、重複しています。 - 不足
「調理方法」の中に「切る」という要素が不足しています。
MECEのメリット
MECEの考え方を身につけることで以下のメリットが得られます。
MECEに考えるコツ
MECEの概念は理解できたけど、いざ自分で考えてみるとなかなかうまくいかないという方もいるかもしれません。
そこで、MECEに考える上でのコツをいくつかご紹介します。
1.1つの視点から複数の切り口で考える
1つの事象に対して、複数の視点から切り口を変えて考えてみましょう。
例えば、カレーの味を評価する際に、味覚だけでなく、見た目、香り、食感といった多角的な視点から分析することでより多くの要素が見えてきます。
この時に目的を意識することが重要です。目的を意識することで必要な視点と不要な視点に分けて考えることができます。
2.図や表を活用する
MECEの考え方を視覚的に表現することでより深く理解できます。
マインドマップや表など、自分に合ったツールを使って要素を整理してみましょう。
3.誰かに説明してみる
自分の考えを誰かに説明することで論理的な矛盾や抜け漏れに気づけます。
友人や同僚に自分の考えを説明し、フィードバックをもらうと良いでしょう。
4.フレームワークを活用する
MECEの考え方を体系的に学ぶために3C分析やSWOT分析などのフレームワークを活用することも有効です。
これらのフレームワークは、MECEの考え方を具体的に実践できます。

フレームワークについては他の記事で解説するよ!
5.練習を積み重ねる
MECEは一朝一夕に身につくものではありません。
日頃から意識して様々な場面でMECEの考え方を活用することで自然に思考が整理されていきます。
6.「なぜ?」を繰り返す
物事を深く掘り下げるためには「なぜ?」という問いを繰り返すことが重要です。
「なぜ、カレーの味があまり美味しくないのか?」という問いに対して、「なぜ、スパイスの量が足りないのか?」「なぜ、火加減が強すぎるのか?」と、さらに深掘りしていくことでより本質的な問題を発見できます。
まとめ
MECEは一見難しそうに思える概念ですが日々の生活やビジネスシーンで意識的に活用することで、論理的な思考力を養い、問題解決能力を向上できます。
この記事で紹介したコツを参考に、ぜひMECEの考え方を自分のものにして、より効率的に物事を進めていきましょう。